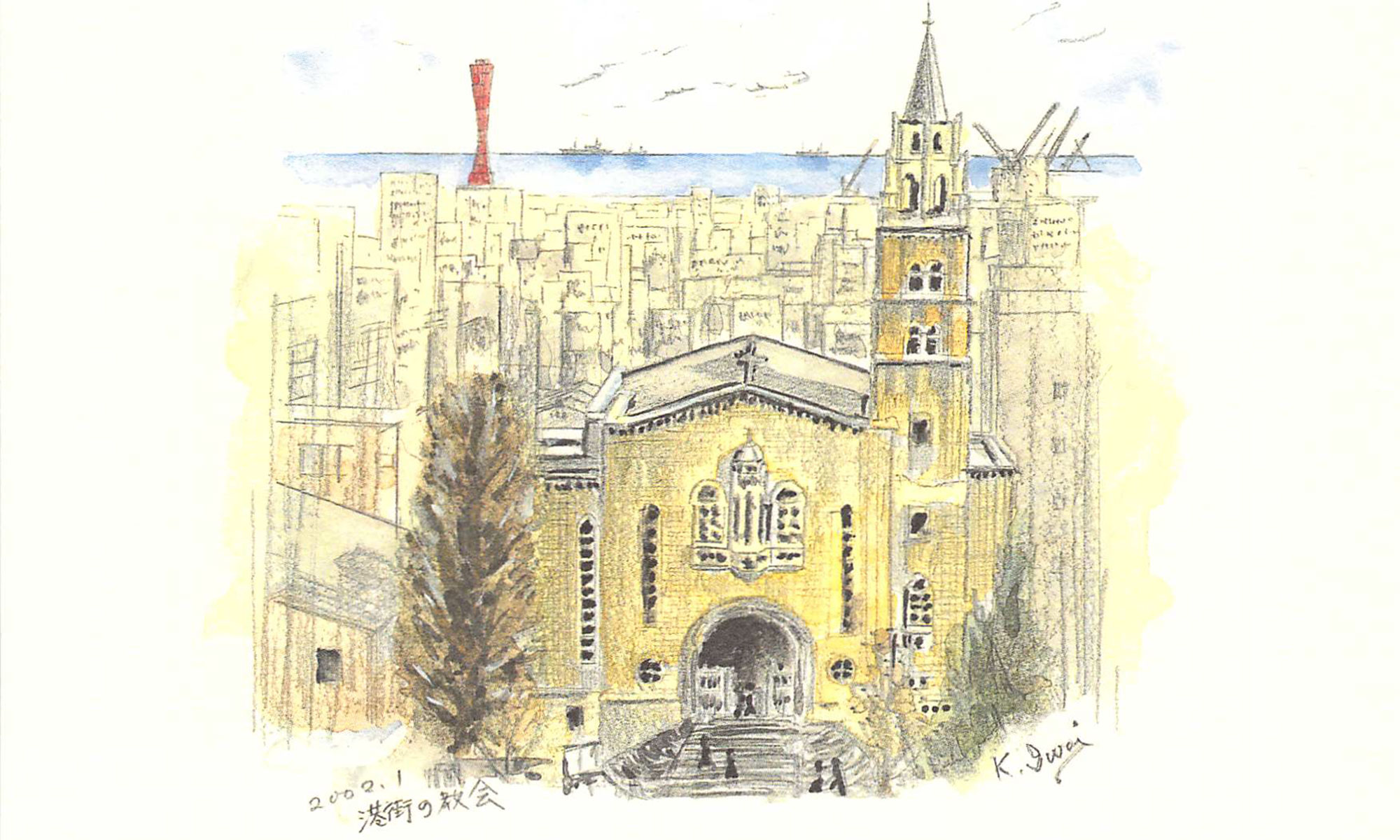2009.5.27(水)12:20-13:00、湘南とつかYMCA “やさしく学ぶ聖書の集い”
「洋画家 小磯良平の聖書のさし絵から聖書を学ぶ」㉒
(明治学院教会牧師、健作さん75歳、『聖書の風景 − 小磯良平の聖書挿絵』出版10年前)
画像は小磯良平画伯「ゲツセマネの祈り」
マタイ 26:36-46、マルコ 14:32-42、ルカ 22:39-46
1.小磯さんの「ゲツセマネの祈り」の挿絵は、苦悩にうちひしがれているイエスを表現している。
上半身を平たい岩にもたれかからせて祈る姿には疲労と困憊が滲んでいる。
ゲツセマネとは「油しぼり」という意味である。
エルサレムの東、ケデロンの谷を隔てたオリブ山の西麓にある園であった。
今は巨大なオリーブの樹があるという。
小磯さんの絵はオリーブの森ではなく、大きく階段状にひろがる荒涼たる岩場として描いている。板状の岩盤の陰影が苦悩の重さを象徴するようにである。
「地面にひれ伏し」(マルコ14:35)「うつ伏せになり」(マタイ26:39)の表現とは違う描き方を小磯さんはしている。
顔を上に向けての祈りの場面である。なぜだろうか。
絵画的表現では「アッバ、父よ」(マルコ 14:36、新共同訳)が表せなかったからではないか。
「アッバ、父よ」は音声であるが、それを絵画で表現するところが難しい。だから、天から差し込む斜めの光が「アッバ、父よ」と、呼び掛けるイエスを包んでいて、絵の中心をイエスの天に向けた顔に光を当てて絞って描いたのではないだろうか。
二人の弟子は岩陰で岩を背もたれにして頭を前に垂れて深く眠り込んでしまっている。マルコは弟子を三人だといっている。小磯さんはマタイに基づいて絵を描いたのであろう。絵の色調は、沈んだ墨絵のように灰色一色である。
2.「いつもの場所にくると」(ルカ22:40)とあるから、いつもそこでイエスは祈っていたのかも知れない。イエスは「ひどく恐れてもだえ始め」(マルコ14:33、新共同訳)、ここは田川建三訳「そして驚愕、困惑しはじめた」が原文に近い。「地面にひれ伏して」(マルコ14:35、新共同訳)、
「アッバ、父よ、あなたには何でもおできになります。この杯を私から取りのけてください。しかし、私が願うことではなく、御心に適うことが行われますように。」(マルコ 14:36、新共同訳)
と祈った、とテキストにはある。テキストの読みを、イエスの祈りの叫びに置くか、弟子の弱さに置くかで、強調点が変わってくる。小磯さんは光を中心にして「祈りの叫び」に強調点を置いた。
3.「アッバ(父)」はイエスが抱いていた根源的なものへの暗喩(ルート・メタファー)の一つだ、と指摘したのは新約聖書学者・大貫隆氏である(『イエスという経験』新教出版社 2003)。
「天の父」という表現はユダヤ教の祈りにもあった。しかし、その表現は家父長的な威厳と遠さであって、子に対する慈愛と近さではなかった。イエスの新しさは、それを破っていることにある。
「アッバ」は、家庭内で幼児が父に向かって用いる、純真な呼び掛けである。また、どんな家父長も率直な子への親愛の瞬間というものがあるものだ。そこに神と人間の関係の類比を見たのは、イエスの独自性だという。
「アッバ」という言葉はイエスでもここが初めて用いられた箇所で「ここに一回だけ」用いられている。その後パウロも用い(ロマ8:15、ガラ4:6)、原始キリスト教であまねく知られる様になったという(マタ11:25-27、ルカ11:2他)。
「アッバ」はイエスの神にたいする最奥からの呼び掛けであったと考えて間違いない。イエスはここに神と人間の関係を表現のモデルを発見した。
4.このゲッセマネの祈りの話は原本マルコが一番詳しい。
「シモン、眠っているのか。わずか一時も目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう、目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても、肉体は弱い。」(マルコ14:37-38、新共同訳)
「あなたがたはこのように、わずか一時もわたしと共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう、目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても、肉体は弱い。」(マタイ26:40-41、新共同訳)
マタイは「目を覚まし」の前に「共に」を付け加ただけで、ほぼマルコを踏襲する。ルカは物語をかなり簡略にして「彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた」(ルカ22:45)と述べ、弟子たちの有様を多少弁護している。
5.弟子に焦点を当てると「共に」祈れなかった、あの眠りが問題になる。
「オリーヴのあぶらの如き悲しみを彼の使徒もつねに持ちてゐたりや」
(斉藤茂吉『白き山』、笠原芳光『言葉と出会う本』法蔵館 所載、p.86より引用)
これは背信の弟子の情景をよく詠んでいる。
6.小磯さんの絵にちなんで、イエスの「アッバ(父よ)」を心に刻みたい。