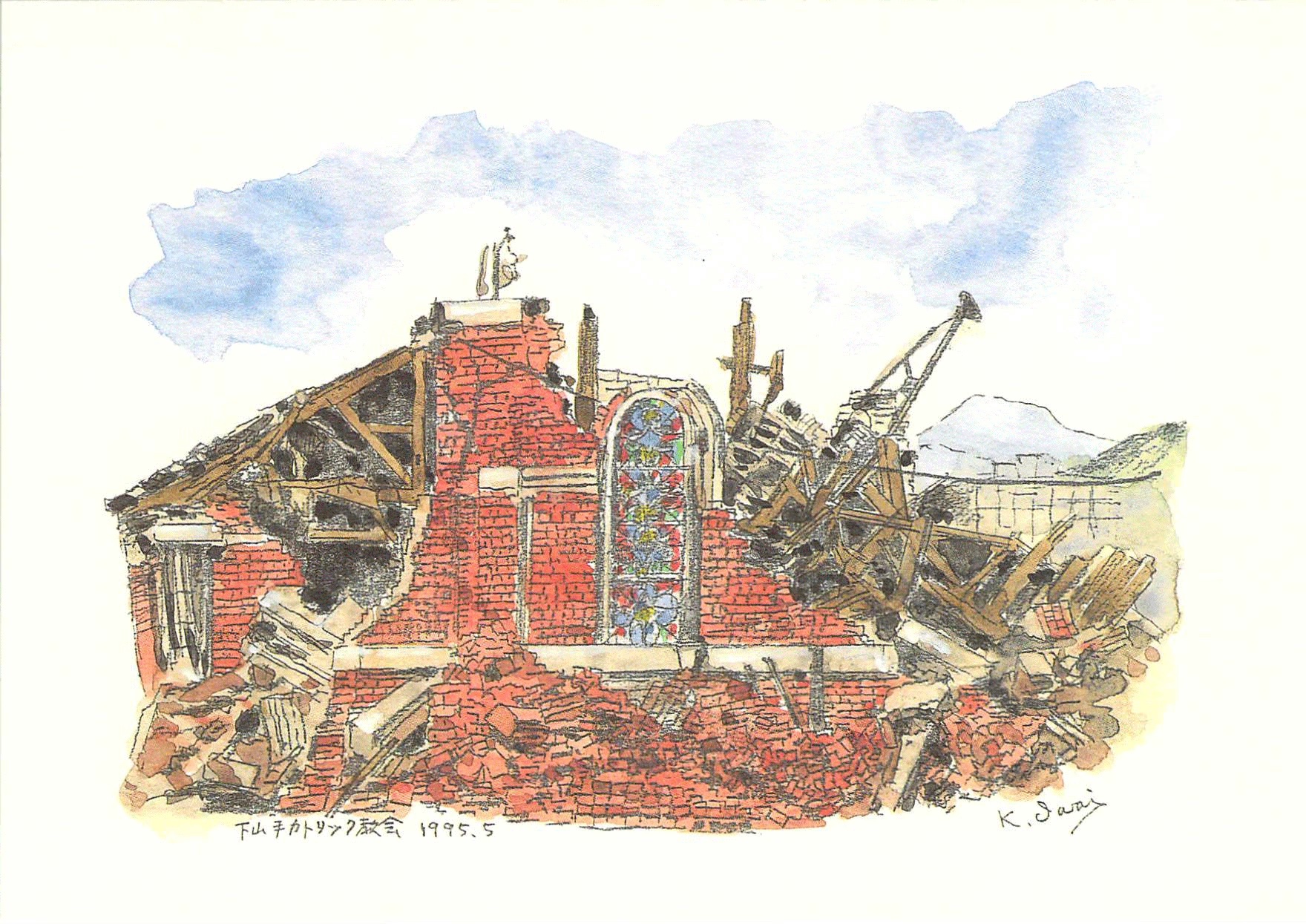1991年7月7日、神戸教会週報、聖霊降臨節第8主日礼拝
(神戸教会牧師14年、牧会33年、健作さん57歳)
”神を見た者は、まだひとりもいない。もしわたしたちが互に愛し合うなら、神はわたしたちのうちにいまし、神の愛がわたしたちのうちに全うされるのである。”(ヨハネの第1の手紙 4:12、口語訳)
「終り」という言葉には、ある種の安堵がある。
起承転結が十分に辿られている事柄には、その想いも静かに漂うであろう。
しかし、人生には「未完成交響曲」のように、未完の終りということがある。
人の目には未完であるものが、それをそれとして「終り」として受け入れるところの究極の根拠は「愛」ではないだろうか。
そんなことを深く考えさせられた本に出会った。
『命をみつめて』(日野原重明、岩波書店 1991年2月/岩波現代文庫 2001年)。
日野原さんは、臨床医としてこの半世紀の間、病を通し、人々の裸の心に接し、家族の一員のようにその交わりに加わり、その死を家族と共に悲しむという体験を繰り返してきている。
氏の人生観はそのように病む人、老いる人、死にいく人々とのふれあいの中で構築された。
その人生観の切なる思いを語った9つの講演が、(1)生を見つめて、(2)死を見つめて、(3)病いを見つめて、の3つに分類され、他に「死の受容」「病気から学んだこと」の2つの論文が収められている。
心を衝く言葉がたくさんある。
”病人は孤独になり、管が喉に入った状態ではものを言うこともできない。多くの患者はそういう状態になって死んでいく。それを見て私は、これが医学のできる最高のものかと、非常にいぶかしく思います。”
”生きるということは、いつも死を考えながら生きるということの一語に尽きます。”
古今の賢人の言葉の引用も多い。
”ただ信仰のみが死を恵みとして受け入れさせる”(タマルティー)
”人は独りで死ぬ”(パスカル)
”私は、幼な心に信じたことを、今もそのま信じている。人生には意味がある。行く先がある。価値がある。一つの苦しみもむだにならず、一粒の涙も、ひとしずくの血も忘れられることはない。この世の秘密は、聖ヨハネのあのことばに含まれているのだ。「神は愛なり」”(モーリアック)
新約聖書の「終り」を示すギリシア語は主に「テロス(名詞)、テレオー(動詞)」。
この言葉の訳は「終り」以外に完全、成就、完全に顕れる、成就する、成し遂げる、走り尽くす、全うする、満たす、となっている。
「テロス」の派生語「テレイオス(名詞)、テレイオー(動詞)」は、公同書簡(特にヘブル人への手紙、ヨハネ文書)によく用いられている。
第1世紀末の初代教会は、信仰の完成を、迫害の中で、一見未完結のように思える地上の事柄の中にも、神による完全、成就を読み取っていたからに違いない。
今日の引用テキストの「全うされる(テレイオー)」もその文脈にある。
”神を見た者は、まだひとりもいない。もしわたしたちが互に愛し合うなら、神はわたしたちのうちにいまし、神の愛がわたしたちのうちに全うされるのである。”(ヨハネの第1の手紙 4:12、口語訳)
(1991年7月7日 神戸教会週報 岩井健作)
翌週に夏期特別集会、主題「詩篇の信仰に学ぶ」
講演:勝村弘也(松蔭女子学院大学教授)
週後半セミナー「キリスト教の現在と未来Ⅱ」司会:岩井健作
YMCAセミナー 7月12日(金)午後6時〜8時半
於神戸YMCA国際文化センター
パネラー:神田建次、村山盛忠