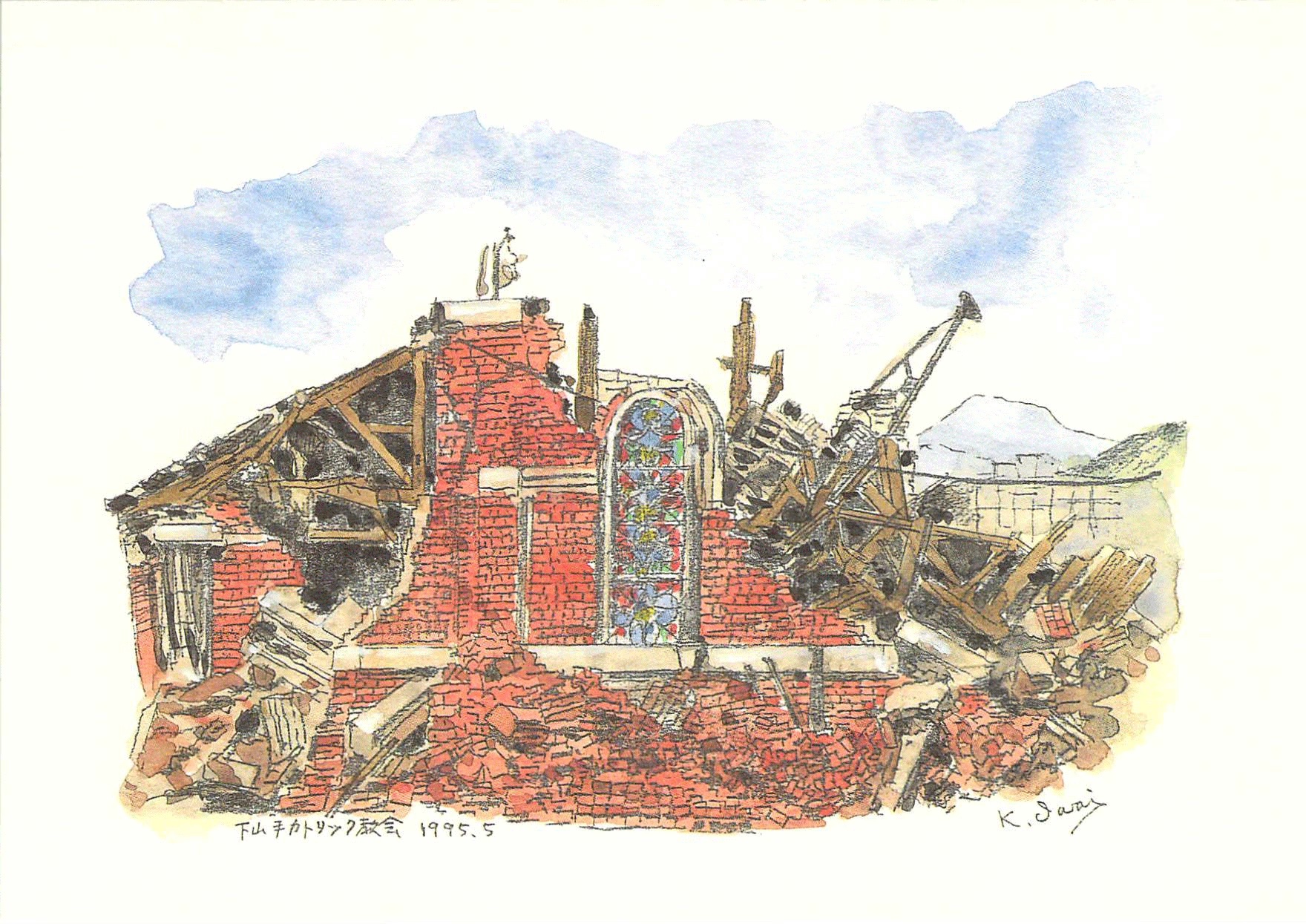2013.6.9、明治学院教会(313)聖霊降臨節 ④
(単立明治学院教会牧師、健作さん79歳)
サムエル上 2:26、マタイ 6:24-34
1.
「花の日・子どもの日」というのは教会暦の中にはありませんが、6月の第二日曜に日本のプロテスタント教会が任意に守っている行事です。起源には諸説ありますが、19世記米国のマサチューセッツ州の会衆派教会で献児式に花を飾って礼拝したことによると言われています。
日本へは大正初期に取り入れられたようです。花を持ち寄り飾って礼拝し、礼拝後は日頃お世話になっている近所の公共施設や病院などを子どもと一緒に訪問する習わしです。子どもが礼拝の主役、という行事として大切にされてきました。
2.花は端的に「神の創造の業」を表し、その「恵み」を示しています。
イエスは「野の花を見よ」と言って、花に象徴される「神のみそなわし(神の支配)と神からの関わり(神の義)」とを「何よりもまず」求めることを強く説きました。
人生の苦労は多いだろうけれども、「思い悩むな」と、とめどもない人間の重い悩みに終止符を打つことを命じました。
そして、「明日のことまでも思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である」と、人を自由の主体へと呼び覚ましました。
これが「山上の説教」の中の「思い悩むな」との有名な説教です。
だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分である。(マタイによる福音書 6:34、新共同訳)
3.
「野の花を見よ」とイエスが言っているのは、花を観察せよということとは違います。観察は知識のために、理科の時間にすることです。花が秘めている神秘への驚きを抱け、ということではないでしょうか。
レイチェル・カーソン(1907-1964、アメリカ、水産生物学者、著書『沈黙の春』)は、子どもは「センス・オブ・ワンダー(神秘さや不思議さに目を見張る感性)」を持っている、それは、人間を超えた存在を認識し、畏れ、驚愕する感性であると言っています。
子どもと一緒にそれを再発見することの大事さを訴えています。
私は、青年前期を農村で育ったので、自然への感性をずいぶん養われました。自然の中に驚きを持って神を覚えることは素朴な信仰でした。
神学校に行って神学を勉強すると「自然の中の神体験」は自然神学といって、キリスト教の正統神学ではない、と言われました。
イエス・キリストによる歴史的啓示以外に神の啓示はない、そのキリスト論的集中こそが神理解において大事である、と教育されました。
イエスという「顔」「体」を持った神が聖書の神です。確かに、今でも、たとえイエスをキリスト論の枠内に置かないでも、イエスを他にして自分の実存はないと思っています。そのイエスが「野の花を見よ」と言っておられるとき、そこには、「センス・オブ・ワンダー」への指示があったのだと思います。
「野の花を見よ」という言葉が、花との出会いの体験を比喩として歴史的啓示を思い起こさせる契機である、とその重さを感じています。
4.
今日、壇上に飾られている花は個性もあり華やかでもあります。でも、「野の」と言われいるように、ありふれた花、どくだみ 、たんぽぽ、野菊、露草の一輪に、神の創造の業を感じないでしょうか。
また、花っけを全く失った、戦場のパレスチナやシリアの民衆の生活を想像し、花は平和の象徴であると思いました。
「野の花を見よ」。ここからの想像力を膨らませて、この季節を生き抜いて行きたいと存じます。