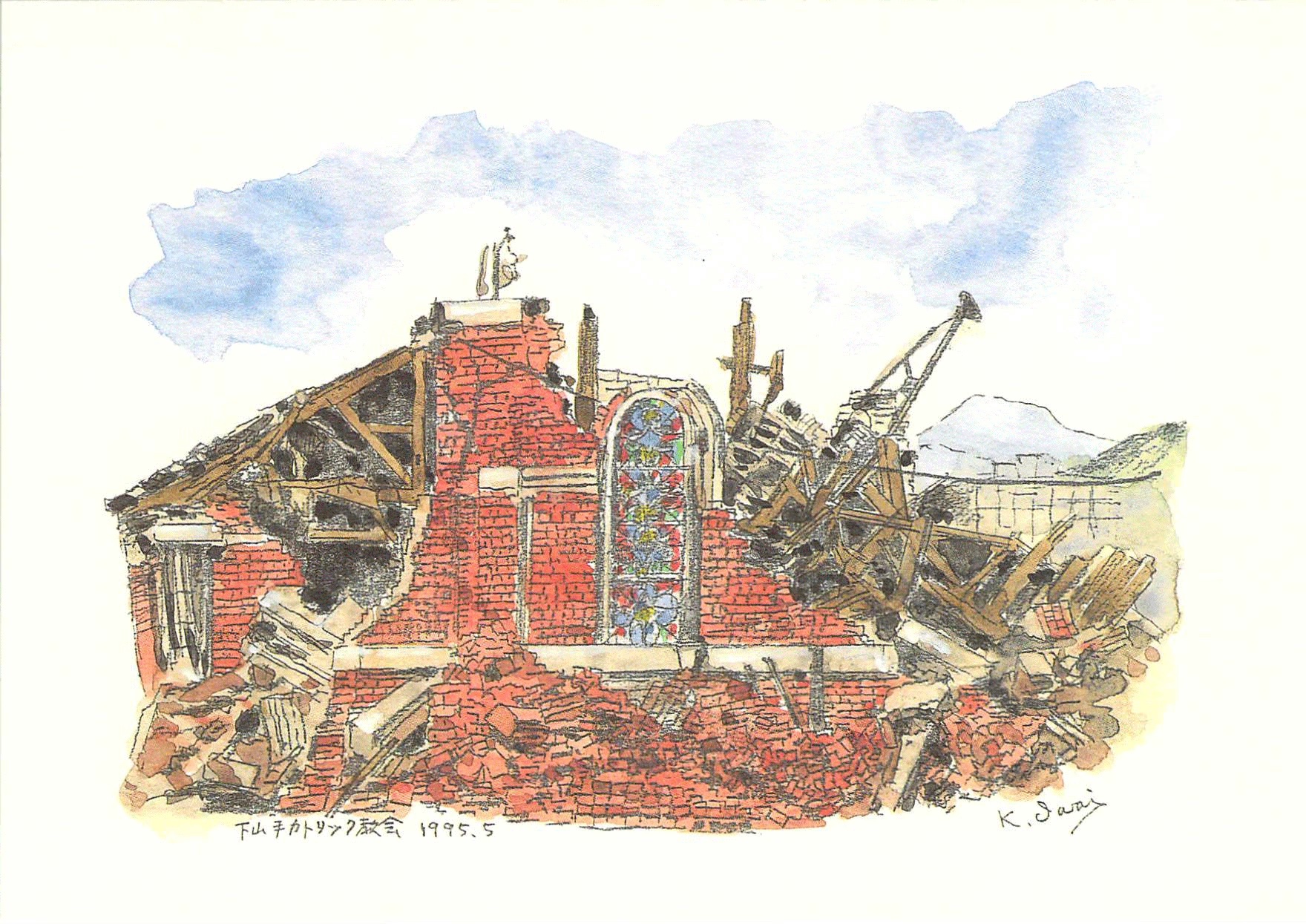2013.5.26、明治学院教会(312)聖霊降臨節 ②
単立明治学院教会創立10周年
(単立明治学院教会牧師、健作さん79歳)
イザヤ 57:14-15、エフェソ 4:7-16
むしろ、愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で、頭であるキリストに向かって成長して行きます。(エフェソの信徒への手紙 4:15、新共同訳)
1.ここは「大学」のチャペルの講壇です。
日曜は教会の説教壇です。大学は理性の府ですから、自ずとチャペルでは理性に訴える話をします。教会では当然、信仰の喚起になる話になります。
「理性」と「信仰」の重きを置き方の違いを示しているのは、マタイ20章(「ぶどう園の労働者」のたとえ)と19章の違いです。
「ぶどう園の労働者」の話は理性に訴える話です。「現代の社会保障」など考えれば経済至上主義では成り立ちません。
「このように、後にいる者が先になり、先にいる者が後になる。」(マタイ 20:16、新共同訳)は当然の理なのです。
19章は信仰の話です。「持ち物を売り払えなかった金持ち」の姿に、ペトロが「わたしたちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました」(マタイ 19:27)と自負を述べます。
するとイエスは「しかし、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。」(マタイ19:30、新共同訳)とペトロの自負を戒めます。
私自身の自戒・反省にまつわるエピソードがあります。
私が50年ほど前、伝道・牧会した教会で受洗した方があります。
後の生涯を惜しみなく教会奉仕されたその方の教会に招かれました。実情はその方はいつの間にか「小ペトロ(教会ボス)」になってしまって、若い牧師や若い教会員が困っていたのです。
「教会」によくある話です。
責任を感じ、荷を共にする役目のお招きか、と思いきや、末期癌のその方への励ましと慰めの役を与えられ、「愛に根ざして真理を語る」教会の存在を感じました。マタイ19章の「先の者は後に」を心に刻みました。実は最近「謙遜」「自分を捨てる」という説教を続けました。当然、自戒を込めてです。
2.「理性」に重きを置く大学は大人の世界です。
でも、教会には「信」そのものの規範である「幼子」が与えられています。
10年の間に「幼児洗礼」を受けた子どもが二人います。教会の根付きを感じます。

この教会が「上倉田」から分かれた時、大学チャプレンが牧師でなかったら立ちいかなかったでしょう。しかし、10年目、不思議な不思議な神の導きで「自前の牧師」を与えられました。
「自前の牧師」を招くまでの少しの間の「お手伝いですよ」とお役目を引き受けた私は来年の春に引退します。
横浜上倉田教会にも「創立10年」のご案内を差し上げ、祝福の言葉をいただきました。10年の根付きを感じます。
無償でチャペルを使用させて頂く代償の印ぐらいはと、社会的働きに毎年捧げています。昨年は50箇所に44万7千円を捧げました。「明治学院(教会)」という名前を覚えて頂く繋がりもできています。
3.「大学」は「理性」の府です。
「真理はあなたたちを自由にする」(ヨハネ 8:32)は理性の句です。
同志社は明徳館の塔にラテン語でこの聖句を刻んでいます。
明学もかつてどこかで掲げていたそうです。今は、教会で代わりに掲げようとの提案があり、この聖句を週報に載せています。
しかし、教会は「信仰(愛・希望)」の証の場です。
「愛に根ざして真理を語り…」(エフェソ 4:15)とあるように「真理」が「信仰・愛・希望」によって裏打ちされるところです。
「裏打ち」とは何でしょうか?
それは、イエスの生涯、その振る舞いと言葉、十字架と復活、すなわち「福音」に包まれて歩む喜びです。