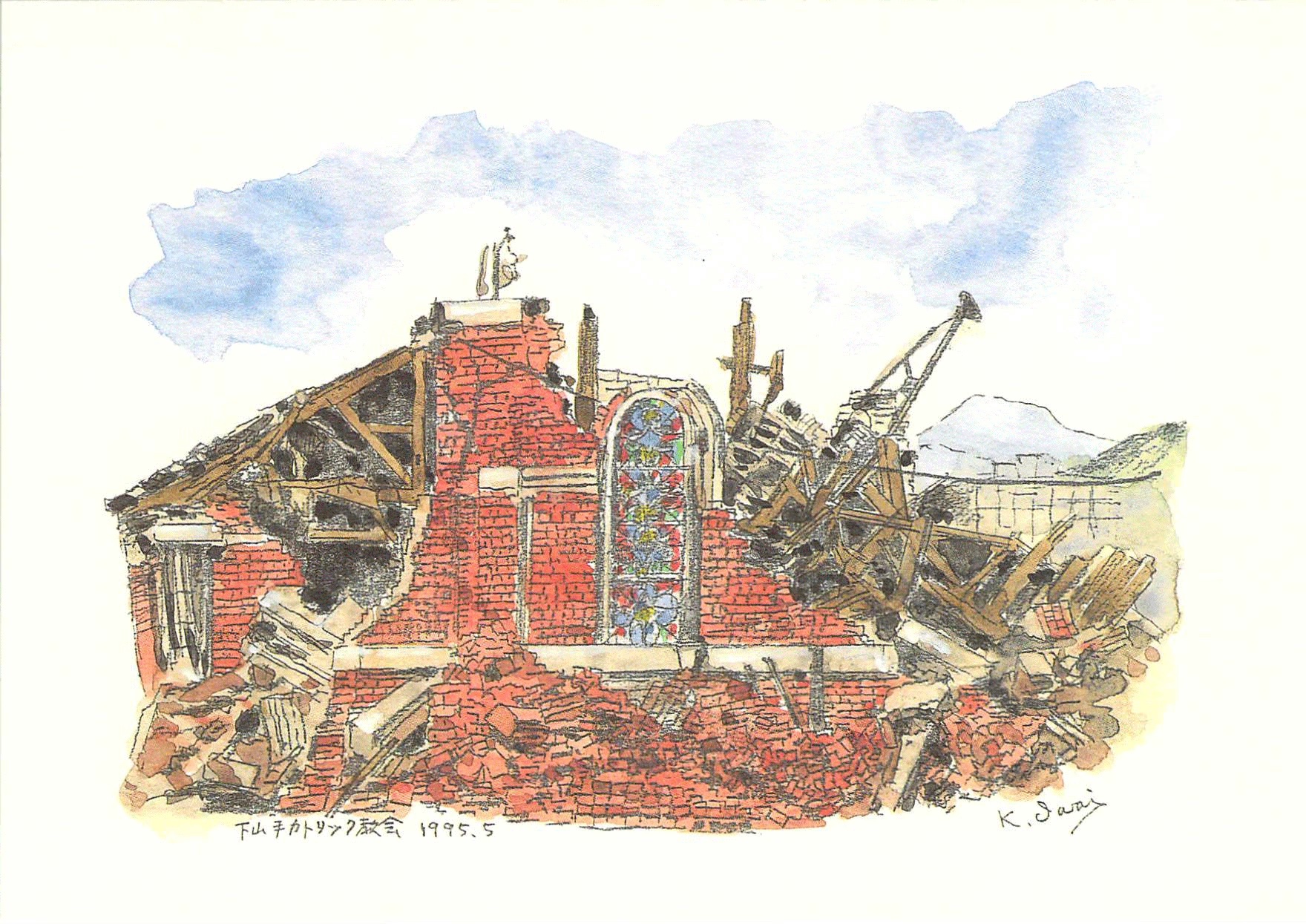2008.11.24(月) 執筆、「求めすすめる会」全国集会用原稿
(日本基督教団教師、明治学院教会牧師、健作さん75歳)
総会議員の皆さんにとっては、一日の議事が終わって、午後9時からという、過重活動の時間帯に、わざわざこのためだけに来られた方も含め約140人がこのテーマで再々結集をしてお集まりいただいたことに感動を致します。
まずは、会場確保にご尽力いただいた京都教区に厚くお礼を申します。
今の教団執行部に欠落していることを一言で申せば『歴史意識の欠如』です。
いや、『救済史』に明確に立っていると反論されるでしょうが、それは神学優位の現実解釈であって、歴史の苦悩を負って生きる「イエスの出来事」すなわち「福音」とは無縁と再反論させていただきます。
教団が現実の歴史を生きるその大事な事柄が「合同とらえなおし」です。
それが今や総会・常議委員会の議題からことさらに外されたのです。
(▶️ 『合同とらえなおし』は運動であるということ ー 運動としての宣教 ②)
しかし、それらは事柄として「戦責告白」を大事にする各個の教会で、心有る信徒・教職有志の運動として、かなりの教区や地区の働きとして担われています。
「草の根」の意識と行動が活きています。

『歴史の証言』(教文館 2004)が最後の出版となって、今年、突如帰天したキリスト教史家・土肥昭夫さん(同志社大学名誉教授・歴史神学 2008年3月31日帰天、享年80)が、同書の7章に「日本基督教団と沖縄キリスト教団の合同とらえなおしと実質化の問題について」を30ページを割いて論じています。
第33回(合同後17回)総会で関連議案が葬り去られて以後の課題を4点指摘しています。
① 日本基督教団の成立過程を含む沖繩教団との関係史を通じて、第4回総会の教憲教規における沖縄県の削除の責任を明らかにすること。
② 「69年合同」の主体性の弱さを沖繩教区は自己批判をしたが、日本基督教団側の批判的検証はできていない。
③ 両教団の歴史認識のずれはあるとしても虚心坦懐に歴史を学ぶことで、最小限の合意を目指すのが課題。
④ その合意に基づき「日本基督教団成立の沿革」の箇所にそれと併列して「沖繩キリスト教団成立の沿革」、両者の下に両教団合同の経過をいれるべきである。「とりあえず、これらのことがなされないと、教憲教規のなかでは両教団合同の歴史的事実が抹消されることになる」。
この4点の指摘は必要最低限度の事柄です。
そうして、これらを解決することで世界の公同教会に連なる合同教会となる(名称変更があれば新しい教会名となる)と、土肥昭夫さんは日本基督教団の教会像を示しています。

「求めすすめる連絡会」は、楕円のごとく二つの焦点を持っています。その一方の「基地撤去」の悲願の課題を、岩国の大川さんはじめ各地の方々の戦いとして今晩もお聞きします。
その戦いの連帯を深め、励ましあうのと同時に、もう一方の課題である、「合同とらえなおし」をすすめることができるような「教団づくり」を課題としてゆこうではありませんか。
今年は沖繩教区が『「沖繩にある将来教会の在り方」答申』(2008.2.13)を出した節目の年です。この答申との対話を含め「沖繩と対話する本土教会の在り方」を草の根で模索していきませんか。
今夜お集まりの方々の平安をお祈りします。