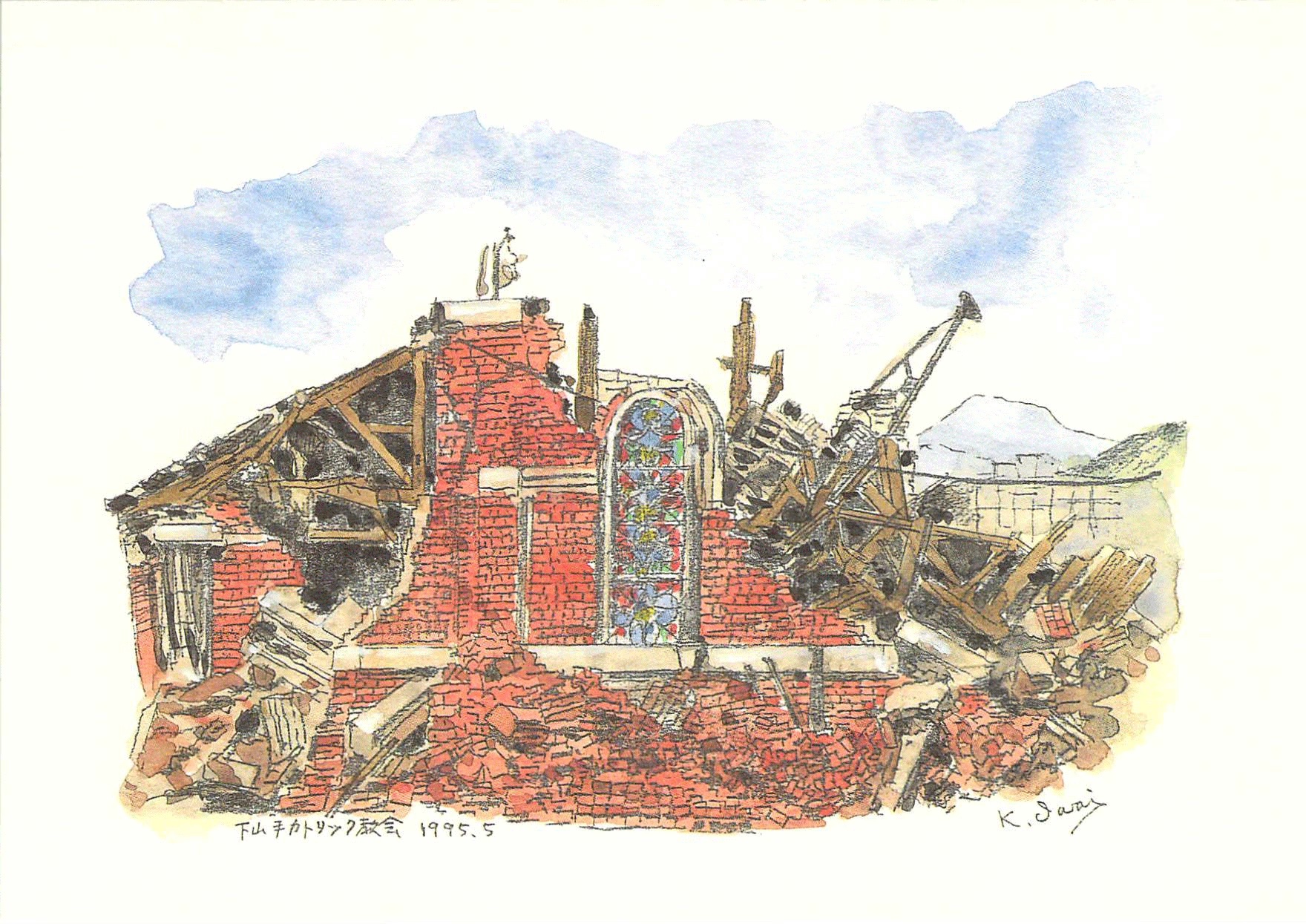2003年5月4日 川和教会礼拝
説教要旨、配布レジュメ
段落2までは説教原稿から
(川和教会牧師代務者2年目、健作さん69歳)
コロサイ 1:9-12
1.先ほどお読み頂いた、コロサイ信徒への手紙1章9節は「こういうわけで」と書き始められています。
これは、コロサイの街にキリストの福音が伝えられて、教会が誕生し、小さい群れではありましたが、実を結んで成長していることを言っています。
教会というものは、神の摂理でそこに誕生し、実を結んで育ち成長していくものだ。その様子を感動的に受け止めているのが「こういうわけで」という言葉です。そして、それだから「あなたがたのためには絶えず祈っている」というのがこの段落の趣旨です。
2.もうしばらく前ですが、『日本基督教団 浦安教会の歩み』という記録集を戴きました。170ページ程の冊子です。年表、写真その時々の週報や会報、教会総会資料などがまとめられたもので、開拓伝道を始めて20年、間借りの開拓時代、土地取得、会堂建築、教会組織の整備などの歩みが伺えます。背景には日本の高度経済成長、新興住宅都市の発展などの条件があって教会が形成してきたことが伺われます。それでも、そこには開拓伝道の意志を持った献身者があり、また教会の核となった信徒の群れが生き生きと息づいています。開拓伝道をし続けた小林晃牧師は、企業に10年勤めた後、献身しました。私は、彼の育った教会の牧会をかつてさせて頂いたので、20年は祈りと共に歩ませて頂いたという思いがあり、『20年の歩み』の記録集は感無量の思いが致しました。その本の中で小林牧師はこう記しています。
「私どもの弱さにもかかわらず、主から託された使命の一端を担って、今日まで進むことができたのは、主の御言葉であり、また多くの教会の方々の支援によるものでした。」(小林晃『日本基督教団 浦安教会の歩み』)▷ 浦安教会のこと(1996)
ここには二つのことが含まれています。
彼が「主のみ言葉」と言っていることと「多くの教会の方々」ということです。言い換えると、福音の出来事そのものの力という面と、それに応えて働いた人々の働きという面です。一方を「神の働き」と言えば、他方は「人々の応答」ということです。
教会の誕生、形成、成長というものは、この二つが相まって成されていくものだ、ということをよく示しているのが、コロサイの信徒への手紙です。先週1節〜8節までのところで学びましたように「福音」は一方で主語であり、一方で目的語なのです。6節ではこう記されていました。「あなた方にまで伝えられて福音は…実を結んで成長している」。ここでは主語です。ところが7節では「この福音をエパフラスから…学んだ」と目的語です。エパフラスの教える努力、コロサイの人々の学ぶ努力がなければ、教会は存在しないのです。6節のところには大変大事な言葉があります。
3.「神の恵みを聞いて真に悟った日から」(コロサイ 1:6)。コロサイ信徒の姿。
ここで「聞く」とはどういうことか。聞いた者が少しでも変わること。イエスの生涯、振る舞い、言葉、そしてその死に方、さらにはその弟子たちがイエスの生き方の全体を復活の信仰として表現した、その出来事の全体に動かされて変わること。
4.「聞いて悟る」とはどういうことか。「知る、悟る」はコロサイ書のキーワード。新約聖書には20回出てくるが、パウロの後の文書にはそのうちの15回が使われている。9節・10節では「悟り、深く知る」と訳される。この語(”エピグノーシス”=認識)は「神の意志に対するしかるべき認識を行動によって確認する」(『釈義事典』Ⅱ, p.54)とあるように行動を伴った把握・体得を意味する。
5.コロサイの街は哲学が盛んだった。それなりに日頃の生活はこの哲学と結びついて考えられていた。しかしそれにもまして、キリストの福音がそれを上回る行動知であることを願うのが、著者の祈り。
6.行動知とは何か。宗教が自分のあり方の反省に作用するなら「知」として健全。だが自分の利益や目的達成の祈願への知であるなら危ない。
7.「神をますます深く知る」ためいは「根気強く耐え忍ぶように」と祈られている。信仰が生活において実を結ぶためには「根気強く耐える」必要がある。(関連箇所:ガラテヤ6:9、Ⅱテサロニケ3:13、ローマ5:4)
8.小塩力氏はコロサイ書のこの箇所の説教で、「ますます神を深く知る」ことについて「恩寵の品位に添う」と言っている。
9.「恩寵の品位に添う」で思い出す人、岩国教会員であった丹下まり姉妹の歌を紹介したい。
唄ひ慣れしわが讃美歌に夫と子等共に和すらむ天つ空より
日毎日毎物忘れ多くなるわれを天国婆と若きらの言う
原形に還元されし安らぎと独り茶を喫み独り花見る
(丹下まり歌集『樹林』)

「根気強く耐え忍ぶ」その先には、こんな信仰の境地があることを垣間見て過ごしたいと存じます。祈ります。
(2003年5月4日 川和教会 礼拝説教要旨)