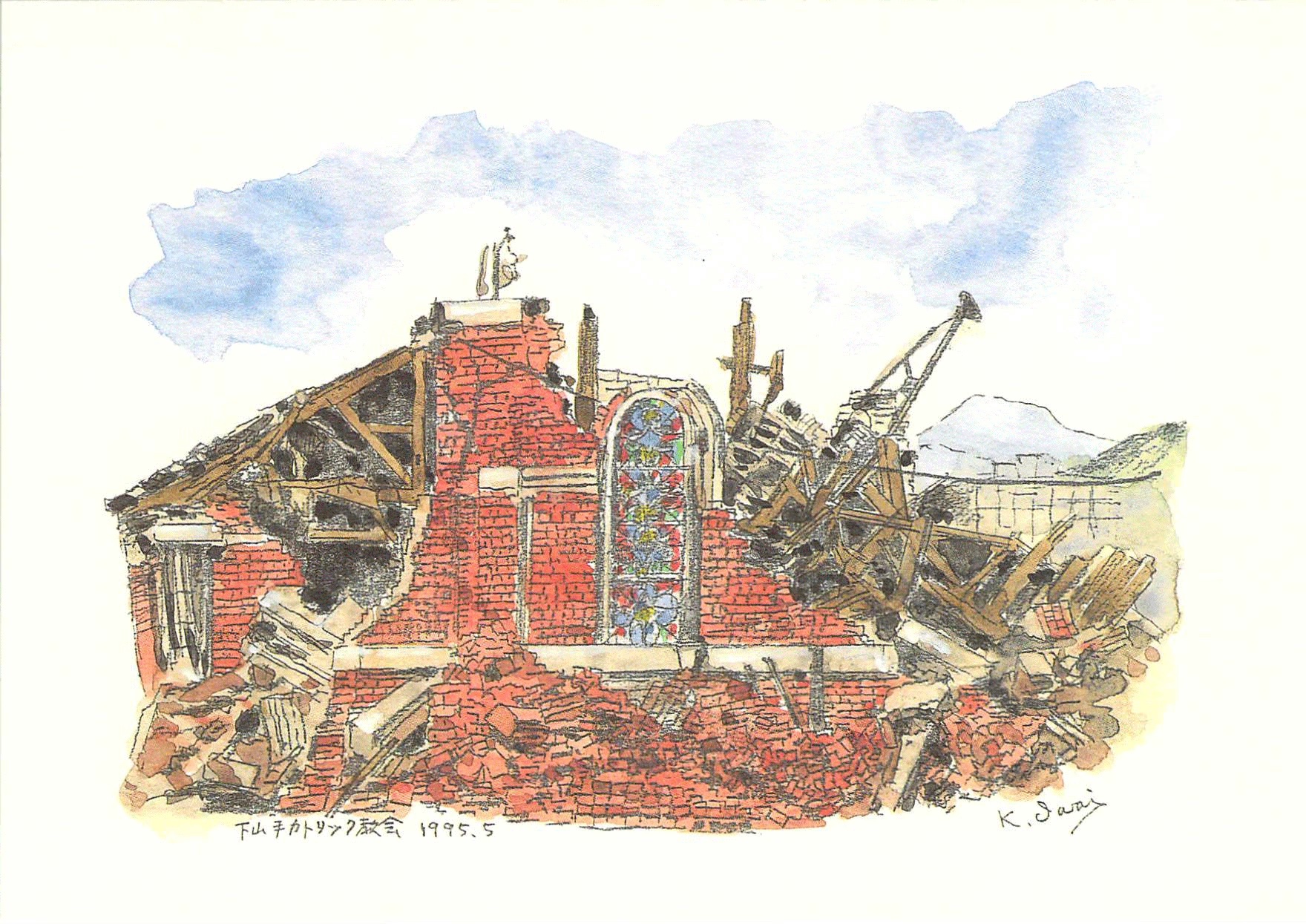1989年7月30日、聖霊降臨節第12主日
(当日の神戸教会週報に掲載)
午後「神戸教会で結婚式を挙げたOB・OGの集い」参加43名
(牧会31年、神戸教会牧師12年、健作さん55歳)
伝道の書 12:1、テモテへの第二の手紙 1:3-5、説教題「造り主を覚えよ」岩井健作
”あなたの若い日に、あなたの造り主を覚えよ”(伝道の書 12:1、口語訳)
”あなたがいだいている偽りのない信仰を思い起している。この信仰は、まずあなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケとに宿ったものであったが、今あなたにも宿っていると、わたしは確信している。”(テモテへの第二の手紙 1:5、口語訳)
結婚式の説教で、マルコ10章7〜8節「人はその父母を離れ、ふたりの者は一体となるべきである。彼らはもはや、ふたりではなく一体である」という聖書の言葉に関連して、私は、夫婦というものの二つの側面にいつも触れさせていただいています。
「べきである」と「である」ということ。
「努力」と「感謝」。
「当為(倫理)」と「存在(信仰)」ということです。
そのことに関して、折々、フランスの農民画家ミレーの『晩鐘』という絵のことを話題にさせていただくことがあります。
夕暮れ。労苦多い農作業を共に終え、おそらく家路につけば子供たちや老人たちが、家族の中心となるべきこの二人を待っていて、二人は家族の諸問題の受容者の立場に立たねばならないであろう、たった一瞬のひととき、それぞれに自らを顧れば、弱き者でしかない二人が、困惑、渇き、懺悔、感謝、願いの全てをかけて祈っている。
それがなにか、結婚式の誓約を終わって、手を互いに握り合いつつ祈る結婚の当事者に重なり合って覚えられることがあるので、話題にさせていただくのです。
教会で結婚式をする意志を持つというからには、両人の精神的生育の背景に、あるいは二人の出会いを通じて、無意識のうちにも、その心の遺産があるに違いない、というのが私の若い人たちへの想いです。
その度に、テモテ第二の手紙の1章3節以下、あるいはピリピ1章6節の聖書の言葉を思い起します。
”そして、あなたがたのうちに良いわざを始められたかたが、キリスト・イエスの日までにそれを完成して下さるにちがいないと、確信している。”(ピリピ人への手紙 1:6、口語訳)
そこには、たとえ今すぐわからなくとも、確かな神の御手の働きがあるからに違いないと。
結婚式が、教会の祈りを背景に、聖書の言葉に神の語りかけを聴くことの中で行われるということは、自分の人生に一つの基軸を持つということです。
その基軸をどう活かすのかは、その後の生活に関わっていると思います。
自分の生と死、夫婦のありよう、女性をどう観るか、子供の人生をどう観るか、どのような教育観に立つのか、社会の問題をどう観ていくのか、等。
聖書の示す基軸は、固定観念・信念というものではなく、神との関係、絶えず神に審かれ、また許される体験、語りかけを聴く、という自分(自分本位・自己固定化)を砕かれるという「関係の基軸」です。
「造り主を覚えよ」とはその意味です。
結婚式は、頂点でも到達点でもなく、出発点、開始の恵みであったことを、心に刻みたいと存じます。
(1989年7月30日 説教要旨 岩井健作)




1989年 説教・週報・等々
(神戸教会11〜12年目)