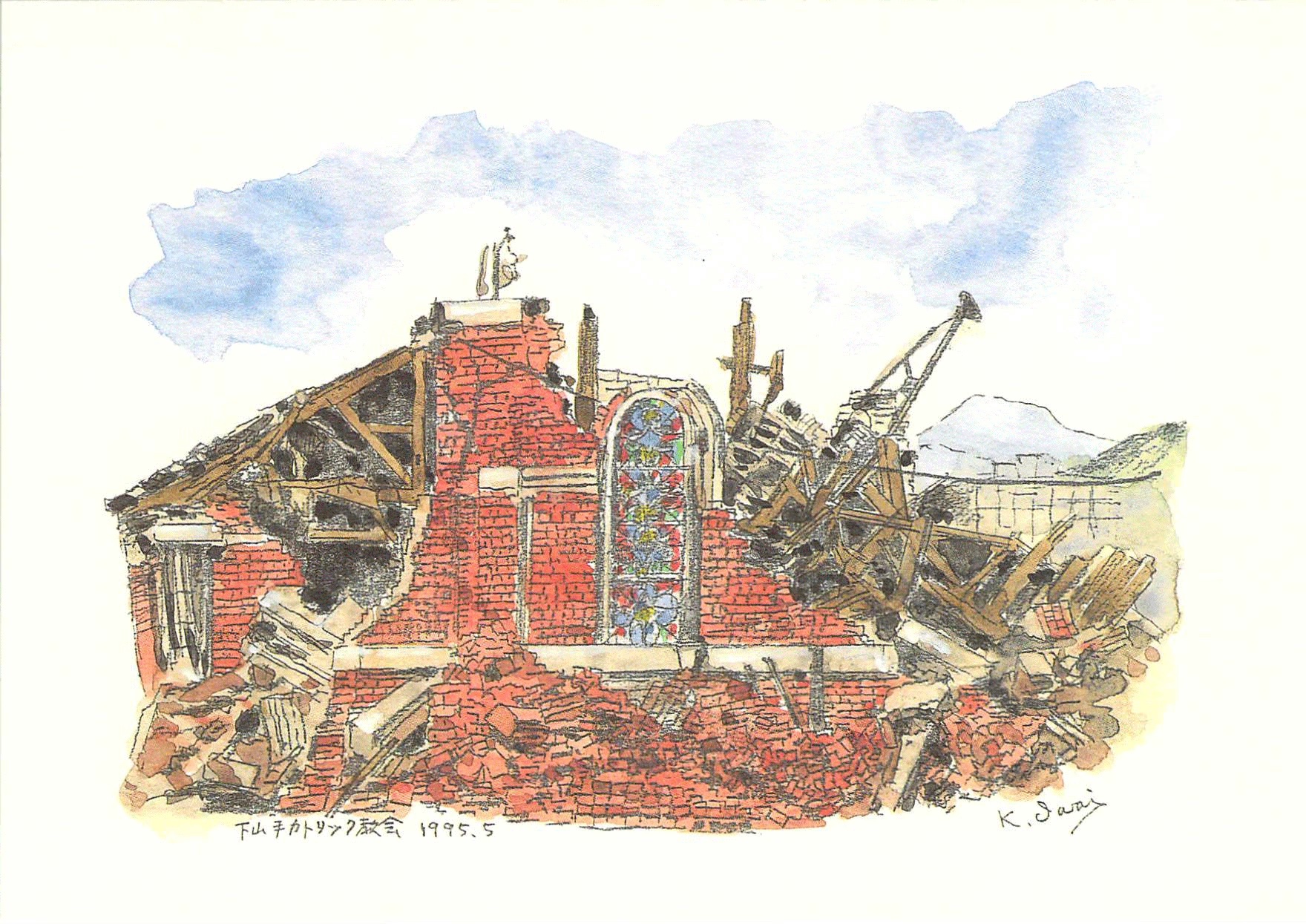2007.12.16、明治学院教会(97)待降節 ③
(単立明治学院教会牧師 2年目、健作さん74歳)
ヨハネの黙示録 3:14-21
1.私たちの生活は様々な暦に網がけされている。太陽暦、暦年、年度、官暦、各種民間暦、季節暦。
時間を暦に意義づけることは生活や思考、価値観の形成に大きく影響している。
12月25日をイエスの誕生の日としたのは、ローマの太陽神の冬至祭のキリスト教化であった。これを中心に教会暦がアドヴェント(待降節)を含めて出来てきた。
日曜日は復活祭から根拠づけられ、カレンダーの週日の初日(神との関わりの日)となった。しかし、最近のビジネス手帳は月曜から始まり、週末を休息として仕事型の思想で編集されている。価値観の違いがある。
2.教会暦には、それに相応しい聖書テキストを教会は選んできた。
今日選んだ「ヨハネ黙示録 3:20」も教会暦テキスト。
だが、それが入ったのはそれなりの歴史がある。
「ヨハネの黙示録」という書物は、ローマ皇帝によるキリスト教への迫害が厳しかった時代、迫害を受けた信徒への激励の書物として書かれた。
ここ(3:14-21)は小アジアの7つの教会に宛てた書簡のうち、ラオデキアの教会宛ての部分の一節。ラオデキアという街は、織物や医学が盛んで、富に重きをおく価値観に埋没していた。教会も例外ではなかった。
だから「冷たくも熱くもない」(15節)、「自分の惨めさ…が分かっていない」(17節)、「だから、熱心に求めよ、悔い改めよ」(19節)と言われ、「戸を叩く」モチーフが続く。
義人は来たるべき世においてメシア(救い主)と食事をするという期待は、ユダヤ教以来の考え(ルカ 12:36参照)。
黙示録の著者は、迫害の真っ只中の教会に、キリストの来臨を告げ、迎え入れることのできる信仰生活を勧めている。迫害を行う側の思想に組み込まれない生活習慣を組み立てるよう勧める。
3.このテキストは、ドイツのプロテスタント音楽家•J.S.バッハが待降節に位置付けた。
彼は、カンタータ(16世紀以降、イタリアの楽器を伴った独唱曲の形式)61番に用いた。
バッハは、礼拝がカトリックの習俗の中に固定化されていた時代、新しい音楽を用いての礼拝の再創造を試みた。
カンタータ 61番のタイトルは「いざ来たれ異邦人の救い主よ」。
「異邦人」(マタイ福音書の東の博士)は、当時、ローマ・カトリックに対して抗議の声をあげたプロテスタント派である自らに当てはめて理解されていたに違いない。
現代的には、社会から疎外された者をさすだろう。
救い主を当然のことのように理解をしていて、危機感を持たないラオデキヤの教会に対して、主は「戸の外から」訪れている。
それは、予想外にも「異邦人の主」なのだ、というメッセージを我々は聞く。
バッハはこのテキストの伴奏に、弦楽器の弾く音を付けている。
我々はクリスマスに弾けて聴こえる様々な叫びに、イエスの「戸の外から」の声を聴き取りたい。


◀️ 2007年 礼拝説教