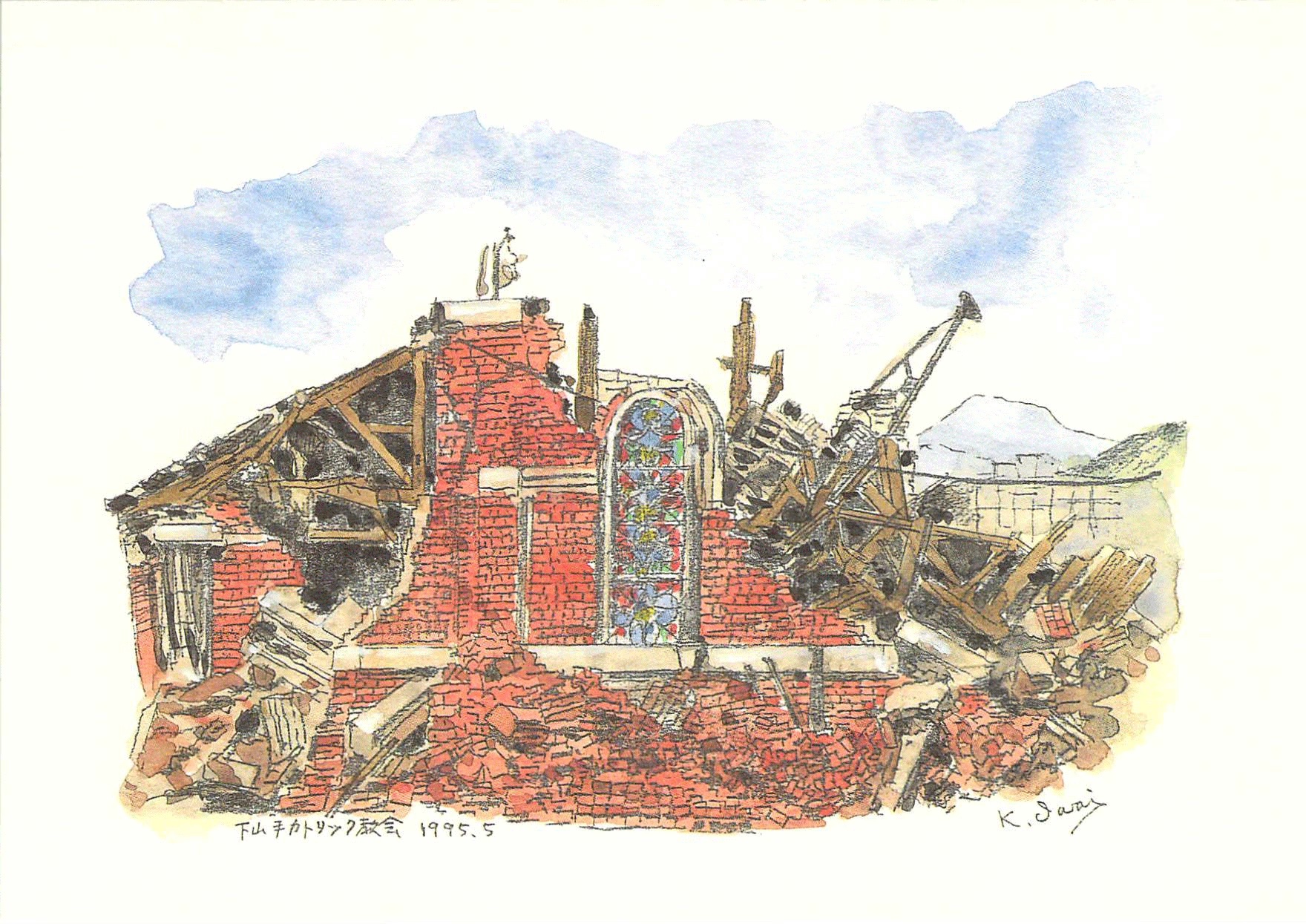1989年12月3日、待降節(アドヴェント)第1主日
箱根出張:11月27-29日、教団宣教協議会出席
(牧会31年、神戸教会牧師12年、健作さん56歳)
マルコによる福音書 13:28-37、説教題「待つ」岩井健作
”それはちょうど、旅に立つ人が家を出るに当り、その僕(しもべ)たちに、それぞれ仕事を割り当てて責任をもたせ、門番には目をさましておれと、命じるようなものである。”(マルコによる福音書 13:34、口語訳)
マルコ13章は「小黙示録」といわれる。
1〜13章までのイエスの振る舞い、教えに関する様々な伝承の編集の結びの部分でもあるし、14章以下の「受難物語」への序曲でもある。
マルコ福音書記者の編集に即して言えば、原始教会が熱狂的に信じ、間近なこととしていた世の終末が遅れていることに対し、キリストが再臨するまでの「中間時の倫理」を説いて、終末論的信仰とは何かを示したものである。
33節「その日、その時は、だれも知らない…ただ父だけが知っておられる」と言う句は、原始教会の信仰告白である。
黙示文学的な表象で語られる言説に惑わされていた原始教会の人たちに対し、終末的大破局を述べる戦慄的な宣言に惑わされてはならない、と戒める。
教会はすでに来たり給うた主と、再び来たり給う主への待望との「中間時」をはっきりと自覚し、すでに啓示された神の救いとやがて成就される救いへの期待の時を、未だ残された使命の時として生きるように、という現在の救いへの招きが語られている。
「いちじくの夏」は収穫の夏であり、季節の終わりであり、始まりである。
古来、教会暦では待降節のテキストとして読まれ覚えられるのは、その故である。
黙示文学的表象をもって世の破局や終末が語られる時、人々が惑わされる様子はいつの時代にもある。
”統一原理運動”や”エホバの証人”等の終末論の魅力と惑わしもそこにある。
そこからは、ルターが言ったように「もし明日世界が滅びると分かっても、わたしはりんごの苗木を植え続けるであろう」という、現在の状況を冷静に受け止め、耐え忍びつつ、待望しつつ、したたかに現在を生きるという生き方は出て来ない。
現在を生きるとは、状況を自分の観念体系に取り込んで解釈することではない。
状況をありのままに認め、受け入れ、耐え、流されず、対峙し、その中に《時の徴(しるし)》を見ることである。
マルコ13章は、その終わりで「門番の譬え」を採用している。
(並行記事にマタイ 24:32-44、25:13-15、ルカ 21:29-37)
共観福音書の引用の仕方が多様であるから、様々な文脈でよく話された話であろう。
(マルコ 13:33、13:35、13:37は編集句)
「目をさましていなさい」はイエスのゲッセマネの祈りでも語られている。
”だから、目をさましていなさい。いつ、家の主人が帰ってくるのか、夕方か、夜中か、にわとりの鳴くころか、明け方か、わからないからである。”(マルコによる福音書 13:35、口語訳)
目を覚ませ。
現在を生きよ。
イエス・キリストに示された神の慰めと希望をもって日々(現実)を生きよ。
そのことを、どう受け止めたかは、私たちの人生の軌跡として残るであろう。
(1989年12月3日 説教要旨 岩井健作)




1989年 説教・週報・等々
(神戸教会11〜12年目)