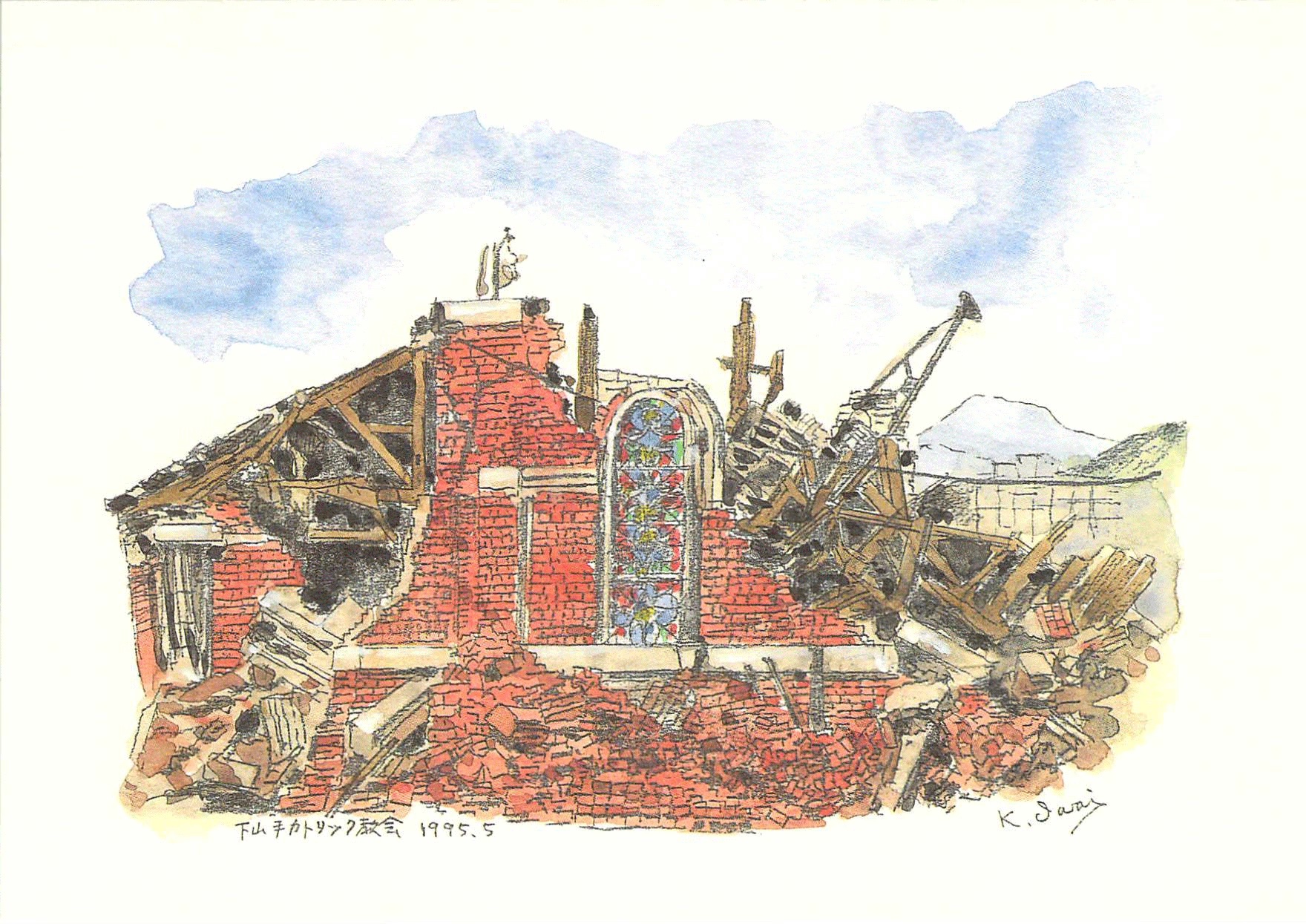1959年11月12日発行、広島流川教会 共励会・学生会
「秋期集会のために」リーフレット巻頭言
集会主題「人間 − 男と女」、11月15−16日
(牧会2年目、広島流川教会伝道師2年目、健作さん26歳)
もやは、ユダヤ人もギリシヤ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。あなたがたは皆、キリスト•イエスにあって一つだからである。(ガラテヤ人への手紙 3:28、口語訳)
朝のバスは通勤者でひどく混んでいた。かなり遅れていたせいか長々と続く乗り降りに乗客も車掌も少なからずいらいらしていた。「発車!」やっと声がかかってギアーの軋む音がした時、すでに閉められたドアへ誰かが手をあげて走り寄った。また停車か、だが次の瞬間、ゆれる車の中で一人の若い女性が皆の目を奪っていた。「車掌が男だからな」そんな囁きも聞こえて何か当然のことのような共感が次々と流れてゆく。皆がオレは男なんだということを秘かに承認しているかの様であった。
確かに男と女の問題ほど人間を自己自身にもどしてくれるものはあるまい。文学がその事を語るのを権利としているように、男と女の関係は人間と人間との間に起こるあらゆる事柄の根源的な範例の様なものかもしれない。
パウロが「もはや…男も女もない。皆、キリスト•イエスにあって一つだからである」と語るとき一体何を言おうとしているのであろうか。ひとまず難解な「キリスト•イエスにあって」というのは後回しにしよう。まず第一に、当時、人種や身分や性による差別の厳しかった古代社会で、とにかく人間が互いに尊厳されるべきであるという、今日で言えば、憲法の精神とでも言うべきものを読みとってよいのではないかと思う。
僕は過日、民芸の"島"を観に行った。観客の組織が伸びないことから演劇不毛の地とまで言われていた広島も、この日、舞台を前にして普段とは違っていた。主人公の学(まなぶ)は結婚まで決意したのに、原爆症という事実の前で、教え子 玲子への愛情を圧し潰してしまう。「先生の弱蟲!ピカの馬鹿!馬鹿馬鹿!」激しい苦しみを訴えて、玲子はそっと立ち去って行き、そして幕がおりた。男や女であることを歪めるような状況を繰り返さぬように自分に言い聞かせながら帰ったのは僕一人ではなかったに違いない。
少し細かい事のようではあるが、「一つである」という言葉は二通りに解釈されている。第一にこの一つは同じという意味に理解される。聖書の思想的系譜をたどると、契約の線上にある。男も女もみな同じ主体とされており、それ故に男と女は対向者であり、「われ – なんじ」の原型でもあるといったことがここで考えられる。ぶどう園で働く労働者の譬(マタイ 20:1-16)などと同例である。
第二に、この一つは分割のできない一対(結合体)を示していると理解される。いわゆる”unio mystica”(神秘的結合)の思想的背景をもっている。互いに異なっているという現状をぎりぎりのところで認めながら、越え難いものをそのままに、なおそれでも一つに結びついているという矛盾を宿した表現である。どちらが妥当と決めつけるわけではないが、註解者諸氏に従って、やはり後者がこのテキストをよく語っていると思う。
ここに於いては「一つである」ということが理由となって、男と女の間の問題が解消されるというのではなく、「一つである」と発言させるエネルギーの反作用が「自分は男であり」「わたしは女なのだ」という事実に立ち向かわせているということに他ならない。
男であり、また女である事を自覚して、うれしくて笑いが止まらぬというような時はよいのだが、逆にその自覚が我々の同胞のうちを暗くするようなこともある。それでもなお、自分自身のけじめを見つめながら「男だの女だのということは問題ではないのだ」と言えたとすればすばらしいではないか。それは目をつぶって第三の性に逃亡するのではなく、自分は男であり、また女であり得るのだという保証を確かめて行くことである。
今日も事務室からの電話で仕事を中断された。何か人生上の相談をしたいという人が待っているという。旅費稼ぎか職の世話か、それとも失恋か家庭不和か。いずれにせよ、これといった解決策など僕は持ち合わせていない。そして男であり女であることがかもし出す人間の矛盾をみつめて2時間。この見知らぬ人と別れて外に出ると、赤みを帯びた秋の日差しが目にしみた。
依然として僕には「イエス•キリストにあって」というのは難解であった。だが、それはそれでよいという気にもなっていたのである。
(広島流川教会伝道師 岩井健作)
書評『キリスト教は同性愛を受け入れられるか』
「福音と世界」2002年7月号所収 新教出版社