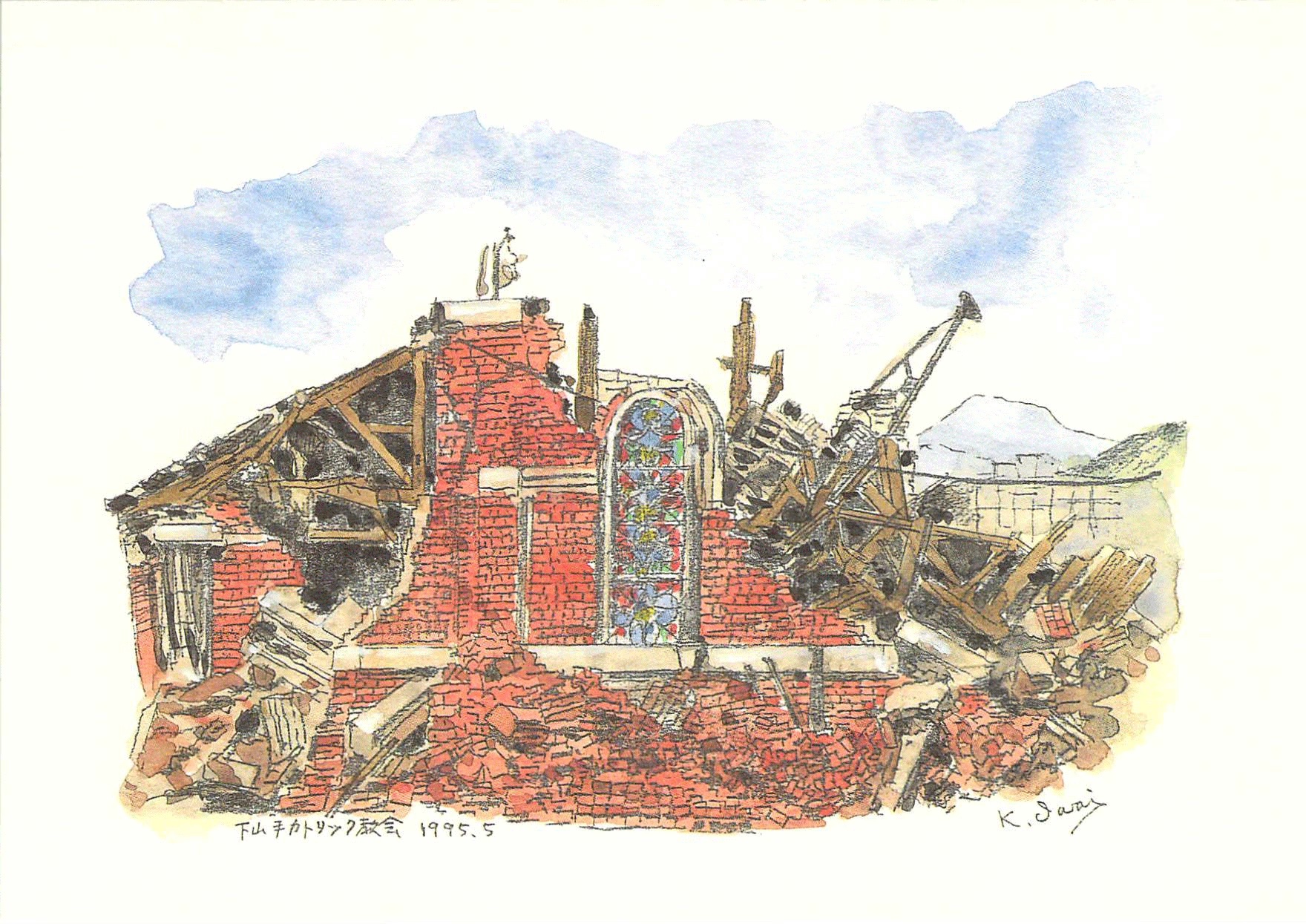2003年7月17日(木)午前10時半
川和教会エマオ会、配布レジュメ
選句「主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら」(詩編130編3節、新共同訳)
Ⅰ.懺悔と赦しの詩編 130編
罪と恵みの本質について本質的な理解を合わせもつ詩編。
ルターはパウロ的詩編の一つにあげる(32, 51, 130, 143編)。
信仰義認を内容とするゆえに。
1〜4節。祈り(二人称)。「深い淵」とは、神からも人からも断絶した関係。
罪の中での無力の自覚。
声と耳への信頼は、人格的存在への目覚め。
神の赦しへの信頼は畏れ(畏敬)を呼び起こす。
5〜6節。悔い改めは待望と緊張関係。
「待ち望む」(”クヮーワー” 27:14, 37:34, 40:1)は緊張関係の意味をもつ。
7〜8節。巡礼歌集に編入される時の加筆。
個人の体験が、共同体(イスラエル)の道しるべとなる。
祭儀の中での反復、想起へと形を整えていく。
「罪」と「贖い」(囚われの身である状態からの買い戻し)の語を用いてイスラエルの解放を歌う。
Ⅱ.聖書の言葉・章句(テキスト)は読み手の文脈(コンテキスト)との関連で読まれる。
詩編130編は、第二次大戦後、戦争協力による信仰の挫折との関わりで読まれてきた。
Ⅲ.沖縄
1.”「在日」「部落」「沖縄」は日本の原罪”(評論家・藤島
宇内 1958)。
琉球処分(1898 廃藩置県)。
太平洋戦争末期の沖縄戦。本土決戦を延ばす意味での戦略。
玉砕戦。沖縄島民を軍属、民間人共に巻き込んだ地上戦。
「本土」出身者軍隊は沖縄民間人の味方ではなかった。
「ひめゆり部隊」「対馬丸」「集団自決」「投降禁止」など。
悲劇。軍首脳による沖縄切り捨て。
米軍占領統治下の過酷な民生。
1972年沖縄返還への闘い。その後の米軍基地体制における本土との格差是認、被差別、被害者性。
2.安保体制強化による沖縄の戦争加害者性。
反基地闘争、土地闘争。地位協定改訂闘争。
Ⅳ.日本基督教団
その成立も問題(1941)
日本基督教団の沖縄教区の放置(切り捨て 1946)
「第二次大戦下における日本基督教団の責任についての告白(戦責告白)」(1967)
「戦責告白」不必要な教会の「信仰告白」堅持派とその教会形成。
「戦責告白」の不十分なところ(沖縄への罪責の欠落と、戦争協力が起きた歴史的反省の欠落)
Ⅴ.「合同」はなされた
「沖縄キリスト教団と日本基督教団との合同」(1969)は「戦責告白」の欠落を補うものとして起こった。
Ⅵ.「合同」の不十分さの指摘が沖縄から
名称、制度は合併吸収。せめて「基督」を「キリスト」へ。
沖縄からの問題提起による「合同のとらえなおし」(1969)
「本土」教団の合併吸収体質。「国家と同質」とは何か。
キリスト教の宣教は「共に苦しみ、共に苦悩を担うこと」ではないのか。
作業の努力。第23回教団総会「合同のとらえなおし」を可決。
「合同とらえなおし」の進展(沖縄との交流)
Ⅶ.現実には教団の諸教会は、沖縄の教会が直面する問題に冷たかった
進展しない面。自分の教会の「教会形成」が第一。
沖縄の歴史や現状を学ばない。教会の歴史を「救いの歴史」として捉え、一般歴史としての沖縄を学ばない。歴史認識の欠落は日本一般のこと。
沖縄の苦悩への無理解、苦悩の抽象化による罪責の希薄さと苦悩の共有の皆無さ。
宣教理解の違い。
「福音はどこで語っても均一とするのか個別状況の苦悩を共に負うことにあるのか」
Ⅷ.教団は冷たかった
さらに教団政治における多数派による「合同とらえなおし」課題の排除。
第33回教団における沖縄教区提案議題「教団名称を、日本合同キリスト教会に変更する件」の廃案。
「沖縄教区常置委員会の声明」が出される(2002年12月15日 教団総会の扱いへの抗議)。
その声明への賛成を建議(神奈川教区総会 2003年6月21日 北村慈郎)の68対66の否決。
沖縄への連帯のための信徒1人1人の署名運動。
川和教会役員会(2003年7月6日)の署名取り組みの承認可決。
Ⅸ.聖書の言葉と意味を今の問題の中で生きたものとしたい
詩編130編を各自はそう読むか。
(2003年7月17日(木)川和教会エマオ会 岩井健作)